「賃上げ(ベースアップ)」が大きな注目を集めています。2024年には賃上げ率が5.17%と、1991年以来の高水準に達しました。一見すると生活改善に繋がるように見えますが、物価上昇や税負担が家計を圧迫し、賃上げの恩恵が薄れるケースも多いのが現実です。
本記事では、賃上げだけに頼らない生活安定の仕組みとして「配当金」に注目し、その可能性を探ります。
1. 賃上げの現状と限界
Contents
1.1 賃上げの恩恵が限定的な理由
- 手取り額の増加が限定的
賃金が月1万円増えたとしても、税金や社会保険料を差し引くと、実際の手取り額は7,000~8,000円程度にとどまります。例えば、年収400万円から410万円に増えた場合、住民税や健康保険料の増加で実質的な手取り額は約6,000円しか増えないケースもあります(日本年金機構 社会保険料の計算基準)。 - 物価上昇が家計を圧迫
2023年の消費者物価指数は前年比2.9%増加(総務省 統計局 消費者物価指数)。例えば、私の家庭では以下のような変化がありました:
- 1週間の食料品代:8,000円 → 10,000円(年間+104,000円)
- ガソリン代:月8,000円 → 11,000円(年間+36,000円)
こうした状況では、賃上げ分が物価上昇に吸収され、実質的な生活改善が難しくなります。
2. 賃上げを補完する選択肢:配当金
2.1 配当金の魅力
配当金は、投資によって得られる「労働に依存しない収入」であり、賃上げに代わる安定的なキャッシュフローを提供します。
具体例:
- 配当利回り4%の銘柄を選んで100万円を投資すると、年間4万円(月3,333円)の配当金が得られます。
- 配当金を再投資することで、10年後にはさらに資産が増え、労働収入に依存しない仕組みを築けます。
2.2 賃上げと配当金の比較
| 比較項目 | 賃上げ | 配当金 |
|---|---|---|
| 手取り額 | 税金・保険料で減少し恩恵が限定的 | 一部課税はあるが優遇措置が活用可能 |
| 収入の増加ペース | 企業業績や経済状況に依存 | 再投資で自動的に増加 |
| 収入の安定性 | 雇用形態や企業業績次第で変動 | 資産運用次第で長期的に安定 |
3. 配当金が広げる生活の選択肢
配当金が家計に与える影響は、単なる収入増加にとどまりません。余裕を生むことで、以下のような選択肢が広がります。
3.1 資格取得への投資
これまで私が取得した資格の例です:
- FP3級:お金の基礎知識を学び、家計管理や投資判断に活用。
- 危険物取扱者(乙種4類):キャリアアップのために取得。
- ITパスポート:デジタル知識を学び、キャリアの幅を広げました。
次に目指す資格:
- FP2級:資産運用の知識を深める。
- 証券外務員:投資の専門知識をさらに磨く。
- 危険物取扱者(他の区分):さらなる専門性を追求。
資格取得にかかる費用(受験料やテキスト代)は、配当金を活用することで負担を感じずに実現できます。
3.2 高性能家電への投資
配当金を活用して購入した家電の一例:
- 洗濯機(Panasonic NA-FA10K3)
高性能かつ省エネモデルを導入し、家事時間を大幅に削減。浮いた時間を家族や自己成長に使えるようになりました。
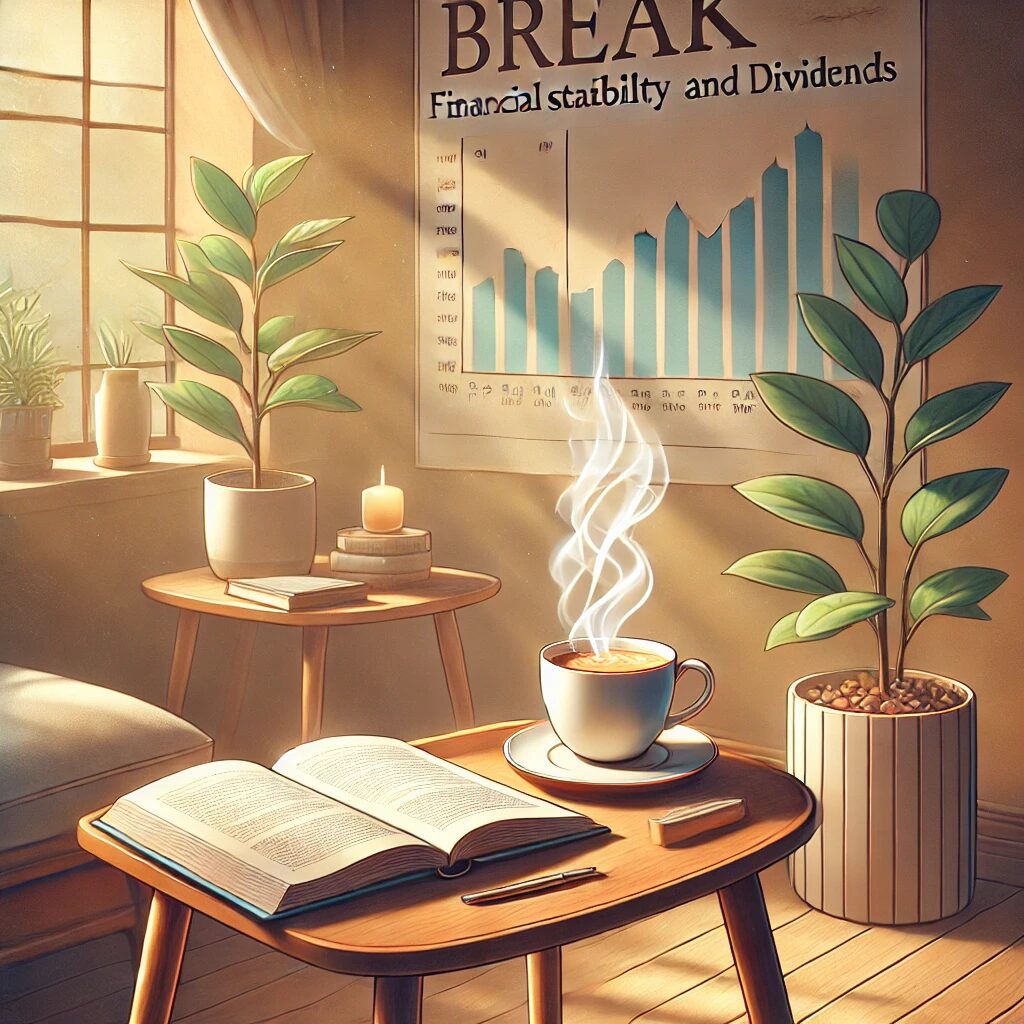
3.3 趣味や副業の準備
配当金があることで、新しい挑戦や趣味への投資も可能です:
- プログラミング学習:オンライン講座で基礎を習得中。将来的に副業としての活用を目指しています。
- 動画編集用PCの購入:副業や趣味で収益化を目指すための準備を進めています。
4. 配当金で月1万円を得るポートフォリオ例
目標:月1万円の配当収入(年間12万円)
配当利回り3~4%の銘柄で400万円の元本を運用することで達成可能です。
| セクター | 配当利回り目安 | 例 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 商社 | 4.0%〜5.0% | 増配実績が豊富な大手企業 | 20% |
| 通信 | 3.0%〜3.5% | 安定収益の国内大手通信キャリア | 20% |
| 金融 | 4.0%〜5.0% | メガバンク、大手保険会社 | 20% |
| エネルギー | 4.0%〜5.0% | 石油・天然ガス関連企業 | 15% |
| 消費財 | 3.0%〜3.5% | 景気に左右されにくい日用品メーカー | 15% |
| 商業インフラ | 4.0%〜4.5% | リースや商業インフラ関連企業 | 10% |
調べ方のヒント:
- 証券会社のスクリーニングツールを活用(モーニングスター 高配当銘柄検索)。
- 各企業のIR情報で配当方針や財務状況を確認。
5. 結論:配当金で広がる生活の可能性
賃上げだけでは解決できない家計の課題を、配当金が補完することができます。労働収入に依存しない仕組みを築くことで、以下のようなメリットが得られます:
- 心の余裕:収入の多様化が精神的な安心感を生む。
- 新たな挑戦:配当金を活用して資格取得や副業準備が可能。
- 家計の安定:物価上昇や税負担の影響を軽減できる。
出典・参考リンク
記事内で使用したデータの出典は以下をご覧ください:



